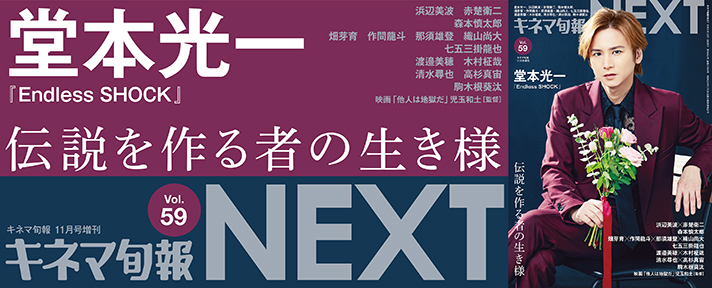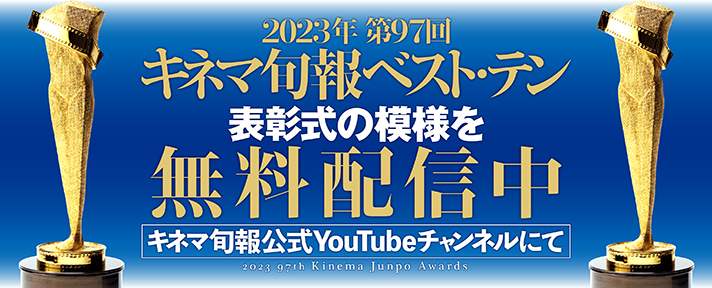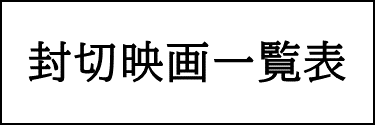「スリー・ビルボード」のM・マクドナー衝撃の戯曲『ピローマン』が東京の舞台に!

2作連続で米アカデミー賞作品賞候補になった「スリー・ビルボード」「イニシェリン島の精霊」の脚本・監督で知られ、今や英語圏を代表する映画作家として君臨するロンドン出身のアイルランド系イギリス人マーティン・マクドナー。彼がキャリア初期に発表した戯曲『ピローマン』が、東京・初台の新国立劇場で上演中である。演出は小川絵梨子。同劇場の芸術監督でもある彼女が、おそるべき猟奇性、情熱、狂気、死生観が乱反射するこの衝撃作を、今回どのように仕上げているか興味は尽きない。キネマ旬報ベスト・テンで「スリー・ビルボード」はみごと2018年の1位、「イニシェリン島の精霊」も2023年の6位に輝いている。マーティン・マクドナーのもうひとつの顔である劇作家としての代表作を、映画評論家・荻野洋一が詳細にレビューする。
今をときめく映画作家の原点=演劇

マーティン・マクドナー脚本・監督の映画「イニシェリン島の精霊」(2022)は「精巧に作られた“嫌な気分にさせる”傑作」と賞賛され、米レビュー収集サイト「Rotten Tomatoes」で高評価率97%を叩き出した。しかしマクドナーにとって、これが過去に執筆した戯曲の焼き直しであることは、意外と知られていない。しかも元になった戯曲「イニシア島のバンシーズ」は執筆当時のマクドナー本人とって不本意な出来だったらしく、破棄されたまま一度も舞台上演されていない。そんな「失敗作」が映画作品として発展的に甦り、ゴールデングローブ賞で作品賞、主演男優賞、脚本賞の3冠を獲得してしまったのだから、作品の運命とはなんとも皮肉な辿り方をするものだ。
マーティン・マクドナーは若い頃から演劇よりも映画製作に憧れており、2010年代以降の映画界における彼の活躍を見ると、「少年時代からの夢をついに実現したのですね」と祝いたい想いに駆られる。しかし今日の彼があるのはやはり、ツワモノひしめくイギリス演劇界において長きにわたり大絶賛のシャワーを浴びてきた演劇作品の数々のおかげである。特に今回上演されている『ピローマン』は2003年にロンドンで初演されてセンセーションを起こし、ローレンス・オリヴィエ賞の新作演劇作品賞を受賞した代表作のひとつだ。
『ピローマン』は日本の演劇人たちも惹きつけ、長塚圭史演出によるPARCO劇場での公演をはじめとして、くりかえし上演されてきた。新国立劇場の芸術監督でもある演出家・小川絵梨子は今回、どのような息吹を同作に吹き込んだのか? 期待感にあふれて場内に足を踏み入れた私たち観客は、センターステージを目撃する。そこには警察の取調室らしき空間に机、椅子、書類棚などが無造作に置かれ、カーテンで仕切られた半円形の怪しげな寝室、そして廊下への出口がしつらえられている。舞台の前後両側に観客席が設けられ、バルコニー席が上段4面を囲んでいる。まるでテニスの選手権会場のようだ。そう、ここは殺人事件をめぐる言葉の応酬をラリーとして凝視するための劇空間であると同時に、過去と現在のラリー、現実と空想のラリー、愛と暴力のラリーにも変化していくのである。
イギリス演劇とアイルランド文学のミックスによる苛烈さ

食肉工場で働きながら、作家として生きる青年カトゥリアン(成河)が、理由もわからずに警察に連行され、この殺風景な空間で尋問を受けはじめる。カトゥリアンは自分が無害な一市民であり、事件にかかわるような人間ではないと弁解し、この逮捕が不当なものだと主張するが、警察側の2人、トゥポルスキ(斉藤直樹)とアリエル(松田慎也)は容疑の姿勢をまったく解こうとしない。カトゥリアンの弁解をよそに、ショッキングな新事実が次々にあらわとなっていき、平和だった現実はガラガラと音を立てて崩壊していく。
『ピローマン』が果敢にも取り扱うのは、毒親による子どもへの虐待、そしてシリアルキラーによる児童殺人であり、こうしたテーマは昔のホラー映画ではごく普通に扱われてきた題材だが、今日においては児童福祉の観点から充分な注意と配慮を要する題材である。マクドナーはそんなリスキーな題材を臆することなく選び、さらにそこにブラックなユーモアさえもまぶしていく。私たち観客はハードな物語展開に震撼しながらも、時おり差し込まれる滑稽なセリフとふるまいに、場内からクククと笑いが漏れるが、その直後に「いま自分は笑ってしまったが、これは不適切な反応だったのではないか」という心配で客席の血の気が引いていく。誰もが非人道的な観客であるとは思われたくはないからである。
思い返せば、イギリス演劇はシェイクスピアの時代から血なまぐさい残酷演劇でもあったのだから、マクドナーの芝居はまさにそうした呵責なきイギリス演劇の伝統の末端にあるのかもしれない。また、アイルランドの血が流れる彼のペンを握る手の平は、オスカー・ワイルドの退廃が、バーナード・ショーの革新性が、ジェイムズ・ジョイスの韜晦が、サミュエル・ベケットの不条理が、そして何よりブラム・ストーカー(「吸血鬼ドラキュラ」作者)の怪奇幻想が、とめどなく脈打っているのだろう。
暴力の連鎖、悲劇の応酬をテニスの試合のように目撃

イギリス演劇とアイルランド文学の折衷、そして作者の映画好きがミックスして創造された劇構造。今回公演のセンターステージ(小倉奈穂の美術による)は前述のとおり、テニスコートのように客席に囲まれ、公開処刑の会場となる。警察権力による取調べも拷問も、カトゥリアンが暗誦してみせる残酷的な物語の再現も、過去に起きた殺人も、児童への虐待も、すべてのことがこのセンターコートで数珠つながりに起こっていく。取調室の片隅の、ほんの数センチの段差で下がっただけの空間で虐待が再現され、薄いカーテンの陰からは少年の悲鳴と金属音が聞こえてくる。そんな生々しい光景を私たち観客はシームレスに受け取らなければならない。
小川絵梨子の今回の意図はそうしたシームレス性にあったのではないか。ロンドン初演を見た長塚圭史の証言によれば、ロンドンでは昇降式の美術セットが採用されていたそうだ。「せりが上がるとスーパーリアルな子ども部屋が現れる。取調室とカトゥリアンの物語世界が往還するようなつくりでした。」(当公演の公式パンフレットより)
今回の小川演出は、ロンドン公演における「往還」とは完全に異なり、シームレスに現在と過去が、取調室と事件現場が、陳述と暴力が、地続きのものとして、すぐ私たちの隣で発生する状況を創造している。ロシアとウクライナの果てしない戦闘が、そしてイスラエルによるパレスチナへの非道な虐殺行為が、決して私たちの日々の生活と無縁ではない地続きのできごとであることとパラレルであるがごとく、すべてのまがまがしい現実/記憶/空想/物語/朗読がこのセンターコートで絵巻としてつながっている。だから、このおそるべき『ピローマン』という演劇作品を見ることは、そこで起こる事件の現場に立ち会うことに等しいのである。
取調室での警察権力とカトゥリアンの応酬を通して、またはカトゥリアンとその兄ミハエル(木村了)とのやり取りを経て、最終的に残るのは物語である。カトゥリアンが少年時代と青春時代のすべてを賭して書いてきた分厚い原稿の束を、彼はすべてを投げ打ってでも残そうとする。これこそ彼の情熱の最後の砦なのだから。どのような苦悩、どのような災禍に見舞われたとしても、自分の書いた物語は残る。カトゥリアンが拘泥してやまぬこの情熱は、マーティン・マクドナーの心からの願望でもあるのかもしれない。そして物語に対する情熱は、演出者・小川絵梨子の耳目によって確かに繋がっていく。小川は稽古中のインタビューで次のように述べている。
「物語というものがどうして我々には必要なのか。もしくはその物語というものが、どう我々の人生に、人間性に影響していくんだろうか。作り手もそうですし、物語を読む我々との関係が明らかになっていく。生きることとか、人生とか人間というものを肯定していくものなんだというのを、私たちに語ってくれるのかなと思っています」(新国立劇場公式YouTubeより)
カトゥリアンも、ミハエルも、さらには警察側の2人にとってさえ、自分たちと物語の関係が重要であることが、芝居を見ていくうちにわかってくる。なぜこれほどまでに物語への執着が作者マクドナーを、そして演出者・小川を衝き動かすのか? ――それは、物語がそれを語る者が確かに生きたというあかしそのものだからである。人間は、このあかしの尊さを知ったら最後、あらゆる困難を経てもなお、どこまでもそれを守ろうとするだろう。『ピローマン』とは、そのことを身を挺して叫び続ける演劇作品として屹立しているのではないだろうか。
文=荻野洋一 制作=キネマ旬報社

『ピローマン』
【公演期間】2024年10 月 8 日(火)~ 27(日)
【会場】新国立劇場 小劇場
【作】マーティン ・マクドナー
【翻訳・演出】小川絵梨子
【美術】 小倉奈穂
【照明】 松本大介
【音響】 加藤 温
【衣裳】 前田文子
【ヘアメイク】 高村マドカ
【演出助手】 渡邊千穂
【舞台監督】 下柳田龍太郎
【出演】成河、木村 了、斉藤直樹、松田慎也、石井 輝、大滝 寛、那須佐代子
【公式HP】https://www.nntt.jac.go.jp/play/the-pillowman/