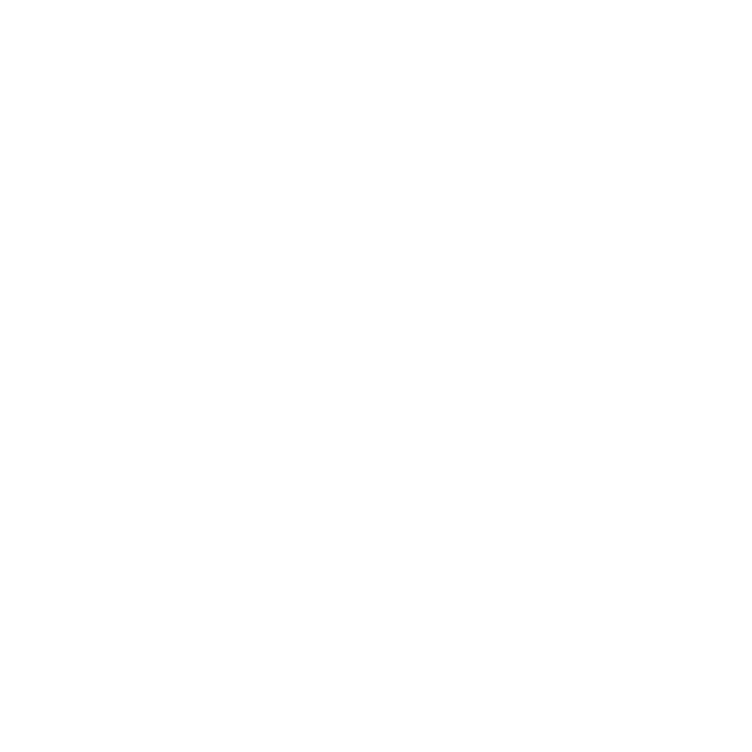結局、予定調和の座組に
この3月の第2週は、とにかく慌ただしい一週間だった。
もちろん山場は2024年3月5日のスーパーチューズデイ。この日のトランプ圧勝の結果を受けて、ニッキー・ヘイリーが大統領選から撤退し、ドナルド・トランプが本選候補となることが確実になった。同日、ジョー・バイデンも危なげなく勝利を収め、唯一まともな挑戦者であった現職下院議員のディーン・フィリップも撤退を決め、こちらもバイデンが本選に進むことが事実上確定した。


結局、バイデンvsトランプの再戦で決まり。一年前から何度も言われてきた通り、現職と前職の大統領である2人の老人が再びリングに上がって殴り合う、という予定調和な結果となった。その戦いにこれから8ヶ月もの間、つきあわされるのだからたまらない。というか、よほどのシンパや政治オタクでもない限り、アメリカ人の大半がこの座組にうんざりしているのが実情だ。であれば、有権者の関心をどのタイミングでどれくらいの熱量で惹きつけるか、その塩梅が、今後、選挙参謀たちの腕の見せ所となる。
さしあたって、トランプ陣営の次なる焦点は副大統領選びである。その選択権を交渉材料にして共和党を掌握しようというのが本当の狙いだ。だからこそ、ヘイリーのようにトランプの拒絶を強く打ち出す共和党員が目立ってきた。トランプにあやかって選挙では勝ちたい、でも、トランプに党を持っていかれるのは業腹だ、だが……という具合に共和党関係者の心はいま大変揺らいでいる。そんな中、今年限りで上院共和党のまとめ役(院内総務)から降りるミッチ・マコーネル上院議員が、スーパーチューズデイ後、トランプ支持を表明した。常に上院共和党の利益になるようプラグマティックに政局を動かし続けてきたマコーネルの決断が、この先党勢にどう影響するかも見ものである。

PHOTOGRAPH: ALEX WONG/GETTY IMAGES
間髪入れずに実施されたキックオフスピーチ
こんな具合に最近の状況を概観したところで、もう少し詳しく3月上旬の動きを振り返っておこう。まず、スーパーチューズデイ当日の3月5日には、ヴァーモントを除いた残り全ての州の予備選でトランプが大勝し、翌3月6日にはヘイリーが大統領選からの撤退を表明した。


その際ヘイリーは、トランプの支持を表明することなく離脱した。同じ5日の予備選で、バイデンも余裕で勝利し、トランプとバイデンとの再戦が確定した。勢いに乗った両名は、翌週の3月12日の予備選で、それぞれ党の指名に必要な過半数の代議員数を確保し、あとは夏の共和党・民主党の全国大会での指名を待つばかりとなった。
スーパーチューズデイの2日後の3月7日には、バイデンが連邦議会でSOTU(=State of the Union)スピーチを行った。70分近く続いたこの一般教書演説は、それまでバイデンについて散々言われてきた「老人」の印象を覆すエネルギッシュで挑発的なものだった。その余波で一気に献金額も増大したほどだ。トランプが対戦相手に決まったところで間髪入れずに行った本選向けの「キックオフスピーチ」であった。
SOTU後の一日でバイデンは1000万ドルの献金を得たという。効果てきめんだった。再選を目指すバイデンのキャンペーンはSOTUから本格稼働した。翌日から総額3000万ドルをかけたキャンペーン広告も大量投下された。そこでもバイデン自ら「オールドマン」であることをネタにしながら、2期目のバイデン政権の姿を語っている。
面白いことに、今年のSOTUについて話題を呼んだのは、怒れる老人を演じたバイデンだけではなかった。毎年、大統領が行ったSOTUスピーチの後には、大統領の所属政党ではない党から、SOTUに対する応答のスピーチがなされるのが慣例なのだが、今年は、当選一期目の共和党の新人上院議員であるケイティ・ブリットが担当した。そのスピーチが物議を醸し、今のリパブリカン(共和党支持者)の奇っ怪さが強調されることになった。42歳で母でもあるブリットが、従来とは異なり、わざわざキッチンを背景にして語りだしたせいもあるのだが、その内容や語り口がキッチンホラーを連想させるようなもので、終わった途端、即座に「スケアリー・マム(背筋凍るママ)」と呼ばれ一気にミーム化し、オンライン上で格好のネタとなった。
いずれにせよ、3月初旬のたった4日間で大統領選を巡る状況は一変した。投票日までまだ8ヶ月を残した「長い長い大統領選キャンペーン」の始まりである。残りの予備選はすべて消化試合となることが決まったため、予備選の盛り上がりもここまでと思ってよいだろう。裏返すと、本選の11月までの8ヶ月間、退屈な日々が続くことになる。結果、バイデンとトランプのあら探しぐらいしかジャーナリズムのやることがなくなってしまった。バイデンに対しては粛々と日々の政務、とりわけウクライナやイスラエルで行われる「戦争」への対策についての精査が続く。一方、トランプについては、もっぱら「訴訟」の進捗状況が伝えられることになる。被告人トランプと米軍総司令バイデンの鍔迫り合い。訴訟と戦争が織り成す大統領選の開幕である。
テンション高めのバイデン
当面のところ、全国大会が開催される夏までは、バイデンは「戦争」、トランプは「訴訟」の行方が報道の主たる内容となる。大勢はこのように決まったが、細かいところを見れば突っ込むべきところは、両者とも少なくない。
バイデンはとにかく現職大統領とは思えない支持率の低さをなんとかしないことには再選の道は厳しい。SOTUの直前までは、まだ選挙当日まで半年以上もあることから、今すぐ立候補を取り下げるべきだという見解も見られたくらいだ。だが、そうした風聞を払拭するくらい、バイデンのSOTUの出来はよかった。問題は、それを接戦州での支持につなげることができるかどうかにある。
SOTUはDCに巣食う政治のプロの祭典であり、政治オタクの祭りである。政治家、官僚、判事、軍人、ジャーナリスト、その他インサイダー向けの一大イベントだ。4大ネットワークを始めとして各テレビ局が中継に入り、今ではストリーミングも欠かせない。そのようなショーアップされた空間で、バイデンは「怒れるオールドマン」を最後まで演じてみせた。


彼が示したのは、老人であることを逆手に取った、〈晩年〉の大統領の凄みだった。〈晩年〉という老い先短い事実がむしろ可能にする不退転の決意である。間違いなくバイデンにとって今年が最後の選挙であり、政治家生命は長くてあと4年ちょっと、という制約があるからこそ真に迫った振る舞いだった。
だからバイデンはSOTUを強く歴史を意識した演説として構成した。冒頭で、FDR(ルーズベルト)、リンカーン、レーガンと、それぞれ第2次世界大戦、南北戦争、冷戦の終結に尽力した大統領たちに言及し、ウクライナやイスラエルで戦争が進行しつつある今、アメリカは再び、そのような戦争の時代に直面していることを強調し、「歴史が見ている」と議場に集まった議員と最高裁判事らに呼びかけた。


この戦争への言及を経てJ6(1月6日議事堂襲撃事件)とIVF(体外受精)に触れ、デモクラシーの守護と、中絶の権利を保障していたロー判決の内容の復活を今後の政策として重視していくと訴えた。いずれも長期に亘る対応が必要な案件であり、事実上、これらの目標は、再選後の2期目のバイデン政権における公約となるものである。そこから、今回のスピーチは、SOTUではなくまるでDNCスピーチ、すなわち、夏の民主党全国大会(DNC)での指名受諾演説のようだと評された。議場は、現在の拮抗した議会を反映して、民主党と共和党の議員の数はほぼ半々だったはずだが、バイデンが気勢を上げるたびに、場内の民主党政治家たちが応え、会場はあられもなくデモクラット(民主党支持者)の祭りと化していた。
実際、トランプという名前こそ出さなかったものの、「私の前任者(my predecessor)」というトランプを示唆する言葉を都合13回も使い、トランプとの対比、トランプへの批判も欠かさなかった。先ほど触れた冒頭部分でも、リンカーンやレーガンなど、共和党大統領の偉業を称えることで、会場の共和党議員からも万雷の拍手を得たところで、一転してプーチンを支持する「前任者(=トランプ)」を批判し、共和党へのジャブを忘れなかった。MAGAを自称するもの以外の共和党政治家の多くは内心、痛いところを突くと苦笑いしていたことだろう。
このように、予想していた以上にバイデンは攻めていた。中絶をはじめとした「リプロダクション・ライツ(生殖の権利)」について言及した際には、会場にいた最高裁判事9名に対して、あなたたちは選挙で選ばれたわけでもないのに政治力を行使したとロー判決の廃止を強く非難した。あまりのテンションの高さから、演説後、共和党支持者たちから、バイデンはなにかクスリでもキメていたのではないかと噂されたくらいだ。
だが、トランプの喋りと比べて改めて気がついたのは、バイデンの口調が政治家としてクラシックなものであることだ。オールドスタイルの語り方であることは間違いないのだけれど、逆に、こういうわかりやすい怒り方もいいのではないかと感じる。
SOTUの演台では大統領の背後に、上院議長でもある副大統領と下院議長がホスト役として控えているのだが、バイデンが共和党の方針に反する政策を語るたびに、後ろにいるマイク・ジョンソン下院議長が顰め面をしていた。だが、時折、無意識にうなずく姿も見られ、今の共和党を束ねる役割の難しさを表していた。

PHOTOGRAPH: AI DRAGO/BLOOMBERG via GETTY IMAGES
リアリティショーとコメディショー
今回のSOTUを見て思ったのは、トランプがリパブリカンにリアリティショーを与えてきたのに対して、バイデンはデモクラットにコメディショーを与えたということだった。
リアリティショーは、現実と虚構の違いを曖昧にした。端的に、虚構の枠組みを外してしまったことで現実との区別がつかなくなった。そうした虚実混じった内容に情動寄りのリパブリカンは容易に翻弄される。一方、反省力があり言語操作にも長けるデモクラットは、ただの作りでは満足せず、風刺なり批判なりが込められている創作物のあり方を好む。現実を距離をおいて把握するための頭の体操となるからだ。
だから、バイデンは、SOTUを意図的にコメディショーにした。「あえて怒れる老人」を演じることでそれは強調された。そうした「演劇調」の建付けを用意した民主党のスタッフからすれば想定外だったのが、ケイティ・ブリットのレスポンスが、完全に「ホラーショー」であったことだろう。多くの人が気づいたように、その様子は、ジョーダン・ピール監督の『ゲットアウト』を彷彿とさせる、ブラックホラーをなぞる構成だった。ブリット本人の言葉というよりも、誰か第3者に無理やり喋らされているような印象を与えるくらいブリットの言動は不気味だった。
その様子はいきなり茶化され、週末の『サタデーナイトライブ(SNL)』では、ケイティ・ブリットを演じたスカーレット・ヨハンソンによって完全にネタにされた。バイデンが用意したコメディは、ケイティを経て、本物のコメディショーにまで伝染してしまったわけだ。だが、それがマスメディアをあてにした政治のこれまでのあり方でもあった。ソーシャルメディア頼みのトランプとの大きな違いだが、ここでも今のリパブリカンが、他でもない自分に向けて語りかけてくれる指導者を欲していることがよくわかる。だから、ロン・デサンティスもそうだったが、既存の政治のルールで育った政治家がトランプの真似をしても失敗してしまう。たとえ第3者から傍若無人と評されようとも、特定の個人にとって意味のある存在であればいいということだ。トランプ支持者がカルト化する理由である。そのためには、ユーザー一人ひとりに語りかけているかのような私秘的なイメージを与えるソーシャルメディアほどふさわしいものはなかった。
バイデンのSOTUの一件は、そうしたマスメディアとソーシャルメディアの違いがよくわかる出来事でもあった。
大統領選の結果を左右しかねないイスラエル問題
ともあれ、これからの選挙戦は、「戦争」と「訴訟」がキーワードである。
さしあたって、バイデンの悩みの種は、イスラエル・ハマス戦争の行方だ。端的にいつ停戦にもちこめるか。できれば夏の民主党全国大会(DNC)の前までには決着をつけ、その成果をもって候補者指名の受諾に臨みたいところだ。
そこで動き出したのが上院民主党のまとめ役(院内総務)であるチャック・シューマー上院議員。3月14日、シューマーは、議会でイスラエルのネタニエフ首相を批判する演説を行い、イスラエル国民に対して選挙によってネタニエフを退陣に追い込むことを強く求める演説を行った。

PHOTOGRAPH: ANNA MONEYMAKER/GETTY IMAGES
ラマダーン前にネタニエフがガザへの侵攻を取りやめ停戦に至らなかったことを非難してのものだ。ニューヨーク州選出のシューマーは、彼自身ユダヤ系アメリカ人であり、つまりは、現代アメリカで政治的トップの地位にあるユダヤ人が同胞であるユダヤ人国家を批判したことになる。アメリカには約600万人のユダヤ系アメリカ人が居住しており、この数は900万人のイスラエルについで世界2位である。それゆえ、ユダヤロビーのアメリカ政界における影響力は強く、長らくイスラエルはアメリカの同盟国の地位を築いてきた。特に民主党との関係が深く、それゆえ右派の共和党からはユダヤ系の批判だけでなく、反ユダヤ主義(anti-Semitism)の言動が現れることも少なくない。典型がQAnon活動家からトランプの後押しで下院議員となったマージョリー・テイラー・グリーンが発した「ユダヤスペースレイザー」という話だろう。ユダヤ人が衛星からレイザーを発射してカリフォルニアの大規模山火事を起こしたという妄言だ。このほかにも今では有名なピザゲート事件のように反ユダヤ主義は、アメリカにおける陰謀論の確固たる源泉の一つとなっている。
もっとも共和党が若干捻れているところは、宗教右派を構成する福音派を中心に、やがて訪れる復活の日に向けた「聖地イェルサレムの確保」という理由からユダヤ系と協調しながらイスラエル支援を続ける人たちがいることだ。こうしてイスラエルは超党派の支持によりアメリカの同盟国であり続けた。
そのイスラエルに対して上院トップのシューマーが批判したのだから、その影響は大きい。おそらくは、カトリックのバイデン大統領が批判をしたならそれだけで不要な尾ひれがついて収拾がつかなくなるため、批判の役を自らユダヤ人であるシューマーが引き受けたというのが実情なのだろう。
というのも、この動きは、単にアメリカの外交政策だけでなく、今年の選挙戦でも大きな意味を持つからだ。端的に、プーチンによるウクライナ侵攻に対して反対するなら、いくら戦端を開いたのがハマスとはいえ、ネタニエフによるガザ侵攻に対しても反対する立場を取らなければ外交姿勢としてバイデン政権には一貫性がないのではないか。そのような批判が、民主党支持者の中からも出始めているからだ。
その結果は、各地の民主党予備選において、バイデンにではなく「uncommitted(該当者なし)」に対して票を投じる人びとが増えてきたところに見られる。これは明らかにバイデン政権に対する党内批判票であり、これをそのまま放置すれば、11月の選挙で彼らは投票には行かず、バイデンのみならず各地の民主党候補の得票数にもマイナスの影響を与えるかもしれない。
今年の大統領選を左右する接戦州は、ペンシルヴァニア、ミシガン、ウィスコンシン、ニューハンプシャー、ジョージア、アリゾナ、ネヴァダの7州と言われており、とりわけ、アラブ系の票も無視できないミシガン州では「uncommitted」の動きは直接、大統領選の結果を左右するものになりかねない。シューマーによるネタニエフ批判はそうした中で行われた。
もっとも、世界中が見守っていたにもかかわらず、ラマダーン前にイスラエルが停戦に向かわなかったことが、選挙戦への配慮だけでなく、アメリカの外交関係者の癇に障ったから、ということもあるのだろう。だからこそ、ユダヤ系のシューマーが、同じくユダヤ人のネタニエフを批判する形になった。
バイデンからしても、今回の選挙キャンペーンのスローガンが「デモクラシーの守護」なのだから、その一貫性のためにもウクライナ戦争とイスラエル・ハマス戦争の扱いを方針として一貫させたいところなのだろう。


イスラエルはアメリカの同盟国だが、ネタニエフはプーチンのような政治家で、同盟関係にもヒビを入れかねないという判断だ。それは、彼らの振る舞いが「デモクラシー」ではなく「オートクラシー(権威主義体制)」に片足を踏み入れているように考えられるからでもある。
ちなみに、シューマーのスピーチの後に、下院議長である共和党のマイク・ジョンソンは、イスラエル支持の表明を明確にした。
訴訟戦略イコール政治戦略のトランプ陣営
このようにバイデン政権が戦争の行方に携わっている間、トランプが従事していたことはなにかといえば、相変わらず訴訟である。
シューマーが演説をした同じ3月14日、トランプは、機密文書持ち出し訴訟のためにフロリダに向かい法廷に出頭していた。4つの刑事訴訟のあいまに民事訴訟に出向く日々が続いている。もはやトランプ陣営においては、訴訟戦略が政治戦略であり、そのまま選挙戦略になるという不可解な事態が続いている。

PHOTOGRAPH: EVA MARIE UZCATEGUI/BLOOMBERG via GETTY IMAGES
戦略の基本は「先延ばし」である。理由をあれこれつけてとにかく訴訟を可能な限り先に延ばし、あわよくばすべて選挙後に審議が行われるようにリスケさせる。そうやって選挙当日まで延期を繰り返したうえで、首尾よく大統領選に勝利した暁には、少なくとも大統領の監督下にある連邦司法省が起こした訴訟については、トランプが指名した司法長官によって取り下げの手続きを取る。トランプが今回の大統領選に出馬したのは、連邦訴訟をなかったことにするためだ、という噂にも頷けるところがある。そのため、大統領就任後の手続きが、最低でもMAGAリパブリカンにとって不自然に感じられないように、以前から、トランプに対する訴訟はいずれも「武器化された政府」によるトランプ個人の失墜を狙った「ウイッチハント(魔女狩り)」であるといい続けてきた。
こうした事態は、報道機関からしても看過できず、勢いトランプについての報道は、「訴訟延期」のリーガル・ストラテジーが中心になり、これがまたアメリカ社会を憂鬱にさせる。なにしろ、白昼堂々ニュースで、どうやって司直の追及を逃れるか、という話が延々なされるからだ。これでは陰謀ならぬ「明謀」「陽謀」である。トランプがいかにズルをするか、リーガル・ストラテジーという名の下で平然と議論される。リーガル・ストラテジーという名の「白昼堂々の陰謀論」を巡る議論。陰謀なら、どうか隠れた潜みでひっそりとやってほしい。しかも、この話をすればするほど、裁判所や司法制度に対する疑念が世間に蔓延していくのだから、引いて見れば、デモクラシーへの不信感を募らせることにもつながる。訴訟社会アメリカの暗部が浮上する。真っ昼間からアメリカ社会システムの転覆方法がジャーナリストたちによって議論されるのだから、真面目なアメリカ市民たちはさぞかし頭を抱えていることだろう。
だが実際に、最高裁の動きが、今回の大統領選で大きな役割を果たしているのだから困ってしまう。たとえば、スーパーチューズデイの前日である3月4日、連邦最高裁は全会一致で、コロラド州最高裁が示した「アメリカ憲法修正第14条第3項に基づき、トランプを公職選挙に立候補することを禁じる」という判決を覆した。理由は、「州は、アメリカ憲法の下で、連邦政府の役職、とりわけ大統領職に対して憲法修正第14条第3条を執行する権限を有していない」というものだ。全会一致とは、保守派6人の判事に加え、リベラル派3人の判事もこの判決を支持したということであり、最高裁としては、争点の一つであるはずの議事堂襲撃事件へのトランプの関与については言及を避け、判断を保留した。
英語で「司法」は“Justice”、「判事」は“Judge”という、つまり司法とは「正義」であり、判事とは「審判」である。その信頼に疑問をきたすような事態が副次的にトランプの訴訟の傍らで生じている。
そのため、トランプを否認すると宣言するリパブリカンがでてきてもおかしくはない。たとえば、3月15日、マイク・ペンスがトランプをエンドースしない、と公言した。一応、その後、バイデンにも投票しないと断ってはいたものの、ペンスの発言は、トランプを支持しない、あるいはトランプに対して懐疑的なリパブリカンに対して、投票所にでかけない、すなわちサボタージュすることを容認するものである。ペンスの影響力がいかほどかは不明だが、少なくとも彼の発言は、NeverTrumperに惹かれつつあるリパブリカンにとってはよい口実・免罪符となるのは間違いないだろう。仮にも、トランプの下で副大統領を務めた人物の発言なのだ。この調子だと、選挙戦中盤では、かつてのトランプ政権の閣僚で袂を分かった人物たちを勢ぞろいさせた「反トランプ広告」が流れることすらあるかもしれない。

PHOTOGRAPH: ALEXI ROSENFELD/GETTY IMAGES
ニッキー・ヘイリーもトランプをエンドースしていない。小さな出来事だが、ヘイリーは、スーパーチューズデイの直前に行われたワシントンDCの予備選で初めてトランプに勝利した。スーパーチューズデイでもヴァーモント州でヘイリーは勝っている。反トランプの勢力は少数ながら(おおむね共和党支持者の3分の1程度)確実に存在する。彼らはトランプの増長をこれ以上望んではいない。
コンサルタント、Design Thinker。コロンビア大学大学院公共政策・経営学修了(MPA)、早稲田大学大学院理工学研究科修了(情報数理工学)。電通総研、電通を経て、メディアコミュニケーション分野を専門とする FERMAT Inc.を設立。2016年アメリカ大統領選を分析した『〈ポスト・トゥルース〉アメリカの誕生』のほか、『ウェブ×ソーシャル×アメリカ』『デザインするテクノロジー』『ウェブ文明論』 『〈未来〉のつくり方』など著作多数。
こうした共和党内の内紛の動きを受けて、今年改選を迎える議員たちが徐々に焦り始めてきた。トランプに投票せずにサボタージュを決め込む共和党支持者がわずかでも増えるようなら、その結果は、大統領選と同じ日に投票が行われる議員や知事などの候補者たちにも少なからず影響を与えるからだ。
改選を迎える政治家たちも予備選の洗礼を受けなければならないため、現時点では迂闊にトランプ批判ができない状況にあり、そのため、報道番組等に出演したときの彼らの発言はいかにも玉虫色で、内心では非常に困惑していることが伝わってくる。だが、以前、ミット・ロムニー上院議員が言っていたように、トランプ批判をしたことで、議員事務所のスタッフはもとより議員の家族にまで危険が及ぶ可能性が高まり、その分セキュリティ費用が増大した、という話もある。そのため、トランプについてのニュースメディアでの受け答えには慎重にならざるを得ない。裏返すと、ペンスの場合は、そのような不安を押してでも立場を鮮明にしないわけにはいかないほど、追い詰められたということだ。
ここまで見てきたように、今年の大統領選は、この先11月まで長く続く憂鬱の中で進められていく。バイデンvsトランプ、という再戦の結果は、むしろ一年かけて振り出しに戻ったような感覚を与える。その徒労感からいかにして立ち直るのか。コロナ禍とは別の意味で、アメリカにとって試練の8ヶ月となりそうだ。