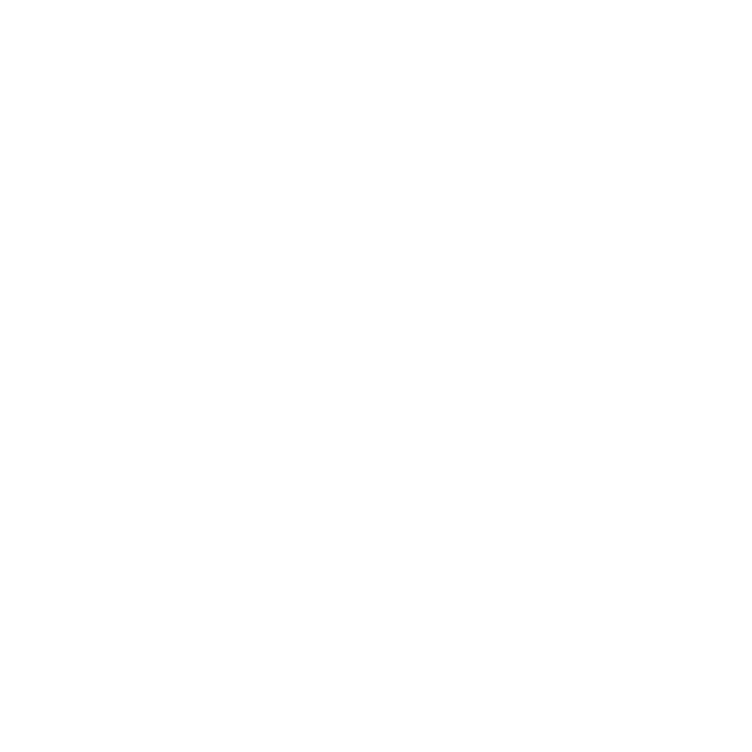Takramのコンテクストデザイナーである渡邉康太郎をゲストに迎え、来たるパラダイムシフトに備える人気企画「ビブリオトーク」を1月30日(火)に実施します。カルチャー、テクノロジー、ビジネスなど、全10分野の最重要キーワードを網羅した最新号「THE WORLD IN 2024」を踏まえた選書と白熱のトークをお楽しみに!詳細はこちら。
真夏のランニングで上半身裸になることがある。トレイルならあまり人に会わないのでまだいいけれど(でも危険なので真似してはいけない)、街中では賛否両論が当然ながらあり、地元鎌倉の夏の海岸沿いでなければいまや特異に映る光景かもしれない。
1964年の東京オリンピックにおいても、「首都美化運動」といったマナーキャンペーンが繰り拡げられた。公園も路上もゴミだらけで列車の車内は「ゴミ箱をひっくり返したよう」であり、日本人は「公衆道徳,公徳心が足りない」と当時の朝日新聞の天声人語には書かれている(日本人のアイデンティティも相当変わったのだ)。当然、“外国人の目のつくところ”で上半身裸でいることもNGだっただろう。
北京をはじめとする中国では、この「男性の上半身裸」がいまも問題になっている。2008年の北京オリンピックの時期にはやはり「マナー向上運動」が起こって一時撲滅されたものの、この数年は「非文明的」ということで明確に禁止する条例が中国各地で制定され罰金刑が科されているという。一部では裸足にサンダル履きも規制されていて、そもそも3シーズンをビーサンで過ごす鎌倉ローカルだったらかなり過酷な内容だ。
ご存知のように日本ではもともと、男女ともに上半身裸でいることは日常的な風景だった。肉体労働者の多くにとってはそれが仕事着だったのだ。いわゆる「文明開化」と西欧化によって、混浴と共にそういう習俗が「非文明的」だとされ禁止・規制されて人々の意識が変わったのは、ついこの150年ほどのことだ。いまでは米西海岸やハワイやオーストラリアのほうが、上半身裸を普通に見かけるようになった。今回の東京オリンピックで上半身裸で旗手を務めたトンガの選手が称賛されたように、自らの“文明”を守り抜いた国々も当然ながら多い。
人々の常識や行動様式、正しいと思える基準や世界はこうあるべきだという合意がいかに劇的に変わりうるか、ということに昔から強い関心がある。それは『WIRED』でも同じで、「IDEAS + INNOVATIONS」という本誌のタグラインは、つまりはそれによって人々の世界の認識がガラリと変わるもの、という意味だ。実際に、創刊からこの30年、インターネットやSNSやAIといったテクノロジーがその劇的な変化を牽引してきた。そして『WIRED』では「クラウドソーシング」や「ロングテール」、最近では「ミラーワールド」という言葉を生み出し、それを通して世界の見え方を永遠に変えてきたのだ。
今週の記事:SFが生み出した造語を網羅する「SF歴史辞典」は、“未来を予測してきた過去”を編み上げる
「Sci-Fi」がテーマの今週のSZメンバーシップの記事で紹介された「SF歴史辞典」が収載するのは、まさにSF的アイデアを言葉にすることで現実をも変えてきた歴史そのものだ。つまり、人々の常識や行動様式、正しいと思える基準や世界はこうあるべきだという合意そのものが、このSFというジャンルが100年の歴史のなかで放射し続けてきた「造語」(新しくつくられた表現)と「新解釈」(古い言葉から成る新たな概念)によって、何度も書き換えられてきた。
そればかりかSFは、「科学が追いつく前から物事を的確に把握してきた」。19世紀のジュール・ヴェルヌによる『月世界旅行』が宇宙開発やロケット工学に影響を与え、カレル・チャペックが戯曲『R.U.R.』で生み出した「ロボット」という言葉は、アイザック・アシモフが短編「堂々めぐり」の中で「ロボット工学三原則」を提示したことで現実の規範となった。
ぼくがかつて邦訳を手掛けたレイ・カーツワイルの『ポスト・ヒューマン誕生』が描いた「シンギュラリティ」も、もともとは数学者で作家のヴァーナー・ヴィンジが93年に発表したエッセイ「The Coming Technological Singularity(技術的特異点の到来)」が初出だ。同じく当時『WIRED』US版編集長だったクリス・アンダーソンの『MAKERS』(2012年)は、メイカームーヴメントの火付け役となったけれど、コリイ・ドクトロウのSF小説『MAKERS』(2009年)に大きな着想を得ている。昨日のFMヨコハマの番組で解説した「メタヴァース」も、いまやフェイスブックも本格進出を表明しているけれど、元々はニール・スティーヴンスンのSF小説『スノウ・クラッシュ』(1992年)がオリジナルだ。
関連記事:フェイスブックが掲げた「メタヴァース企業」という目標と、その本質との埋めがたいギャップ
93年に『WIRED』創刊号の表紙を飾ったSF作家でサイバーパンクの旗手であるブルース・スターリングは、SF的想像力によって未来を大胆に構想しバックキャストでその道筋をプロトタイプしていく手法を「デザイン・フィクション」と名付けた。そしていま、『WIRED』日本版が立ち上げた「Sci-Fiプロトタイピング研究所」はまさにその実装を担っている。研究所のいくつかの大型プロジェクトを進めるなかでぼくが何よりもSFの優位性だと感じるのは、ひとつは非連続な未来を描けること、もうひとつは「人の営みが含まれたナラティヴ」だということだ。
つまりこういうことだ。科学やテクノロジーのSF的な(非連続の)進化は、それがどんなに破壊的で革新的なものであろうとも、それ単体ではナラティヴは始まらない。今回のCOVID-19によるパンデミックが生み出した“非連続な未来”とは、ウイルスによって多くの方々が罹患し亡くなっていること自体ではなく(それは未来ではなく予期された現実だ)、ロックダウン(緊急事態宣言)によってピヴォットを余儀なくされた人々がいま始めている新たなビジネスモデルであり、ライフスタイルのことなのだ。
こうしたナラティヴは普遍的ではなく一回的でもある。最新鋭の蒸気機関という産業革命の成果は太平洋横断を可能にし、結果として極東の島国の人々の裸への感性を永遠に変えることになった。その極東の島国においては、SNSというテクノロジーが57年ぶりのオリンピックをきっかけとしてキャンセルカルチャーを生み出すプラットフォームとなった。
ブルース・スターリングやウィリアム・ギブスンが築いたSFのジャンル「サイバーパンク」においては、結局のところ「首都美化運動」の成果ではなくそこで隠そうとした、混沌としたカオスとしての東京や「チバ・シティ」が描かれ、そこに言葉とナラティヴを与えている。そして、いまや現実になろうとしているのはそのサイバーパンクの世界なのだ。
今週の記事:現実はかつてないほどサイバーパンクの世界に近づいている:マイク・ポンスミス、サイバーパンクの復活を語る
現実がますます管理され、予測され、矮小化される時代において、ぼくたちの価値観や行動様式の非連続な変化は、サイエンスやテクノロジーそのものによってではなく、それに対する人々のリアクションのなかから生まれてくる。その「人々の営みが含まれたナラティヴ」を提示するのは(その上半身が裸かどうかはともかく)SFがもつ本質であり、だからこそぼくたちは、今日もまたSFを読み続けるのだ。
『WIRED』日本版編集長
松島倫明