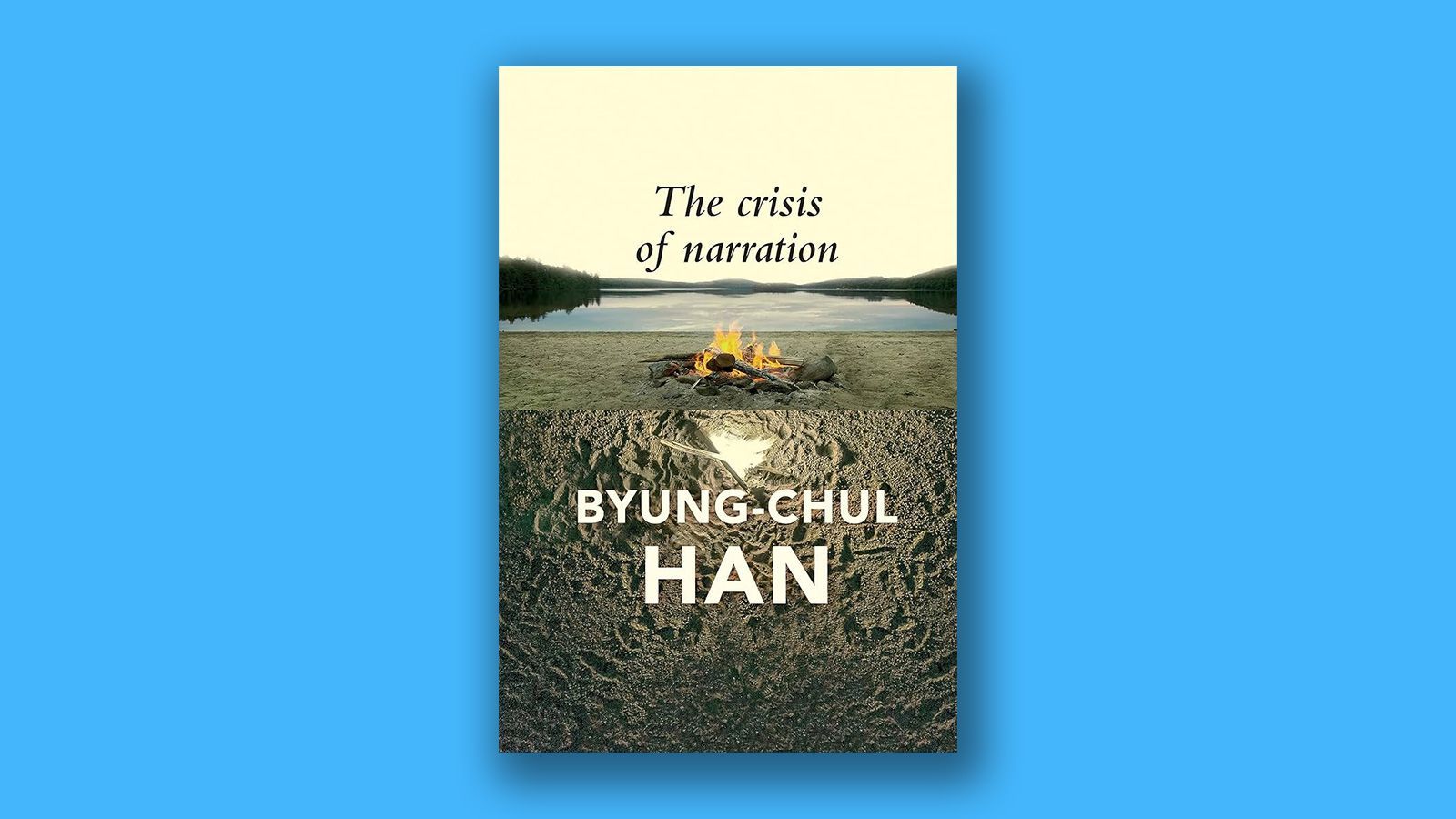「人生を変える力は、ひとつの段落、ひとつの言葉から生まれる」と、ジェームズ・ソルターは1975年の小説『Light Years』で書いている。ソルターによると、たった1行の「スレンダーな」文章との出合いによって、読者は新しい軌道に放り飛ばされ、それを読む前後で人生が二分される。アイダホ大学で芸術学を学ぶケビン・マレーにとって、その瞬間は『In the Swarm: Digital Prospects』(未邦訳)を読んだときに訪れた。それは哲学者ビョンチョル・ハンによる短めのモノグラフ[編註:特定分野の問題に関する学術書]で、最初の英訳は2017年にマサチューセッツ工科大学出版局から刊行されている。
23年5月、マレーはInstagramの画面をスクロールしていて、ハンの著作を解説する動画を見つけて興味をそそられ、大学の図書館で『In the Swarm』を借りてきた。挑発的で格言めいたところのあるハンの文章には、SNSで育ったマレーの経験に合致するようなことがうまく表現されていた。またそのおかげで、自分とインターネットとの関係について感じていた制御不能な感覚が明確になったという。先日インタビューしたとき、マレーは同書のお気に入りの一節をいくつか紹介してくれた。例えば、「デジタル・パノプティコンの住人は、とらわれの身にあるのではない。住人は偽りの自由に身を置いている。自分自身を展示し、自分の生活のあらゆる部分に光を当てることで、デジタル・パノプティコンに情報を供給しているのだ」[編註:パノプティコンは哲学者のジェレミー・ベンサムが18世紀末に構想した円形の刑務所]。マレーはこの本について、「初めて読んだとき、2時間で読み終えた」と教えてくれた。
それ以来、マレーは『In the Swarm』を図書館から借りたまま、お守りのように持ち歩いている。「家の近くのカフェや野原に歩いていくときも、これならジャケットのポケットに入るからね」。彼はハンのほかの著作も買いあさった。『透明社会』、『Saving Beauty』(未邦訳)、『The Agony of Eros』(未邦訳)など、どの本も声明書と評論の中間といった小冊子形式で、ほとんどが100ページに満たない。
マレーのように、ハンをインターネット時代の一種の賢人として信奉する読者が増えている。サンフランシスコのギャラリーでアシスタントとして働く20代のエリザベス・ナカムラも、似たような経験をしてその一員となった。新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるロックダウンが始まったころ、Discordのチャットで、ハンの本をチェックしてみたらどうかとすすめられたのだ。そして彼女は、海賊版の電子書籍掲載で知られるウェブサイトLibgenから『The Agony of Eros』をダウンロードした(彼女が持っているハンの本はすべてPDF形式。デジタルの「サミズダート」[編註:旧ソ連時代に、発禁となった書物を反体制派が複製して流通させた地下出版物]のようなものだ)。
このモノグラフでハンは、SNSが助長する過剰な露出と自己顕示によって、真にエロティックな体験をする可能性は葬られたと主張している。そうした体験には他者との出会いが必要だからだ。「この本を読んだときは『クイーンアウト』という感じだった」と、彼女は喜びを抑え切れず黄色い悲鳴を上げる様子を表すZ世代の言葉を使って説明した。さらに、「一種のミームね。笑えるからじゃなくて、簡潔な感じで拡散しやすいという意味で。これなら、あまり本を読まない友達に、何か考えるきっかけとして送ることもできる」と語った。ハンは、いわばデジタルスクリーン時代のサルトルとして、デジタル生活で誰もが感じている、絶望とまでは言えない無力感を言葉にしているのだ。
2010年の『疲労社会』でブレイク
1959年に韓国で生まれたハンは、実用的な分野に進むことを望む両親をなだめるために、当初はソウルで冶金を学んだ。そして、22歳のときにドイツに渡った。そのまま勉学を続けると約束していたが哲学に転じ、マルティン・ハイデガーの研究に力を注いだ。94年にフライブルク大学で博士号を取得すると、その後は現象学、美学、宗教を教え、最終的にベルリン芸術大学に職を得た。
過去20年にわたって切れ目なく著作を発表してきたが、インタビューは受けず、ドイツ国外に出向くこともめったにない。ハンの著作を2017年から14冊刊行している英国の独立系出版社、Polityの社長を務めるジョン・トンプソンに話を聞くと、ハンの著書への需要は主に口コミで増えているのだという。「ビョンチョル・ハンは草の根レベルで受け入れられていて、それが需要を押し上げている。主要メディアの書評といった一般的な方法とは違う」。トンプソンはさらにこう続けた。「彼はまるで発動機だよ。アイデアと著作が次々に湧き出てくるんだ」
ハンが大ブレイクするきっかけになったのは『疲労社会』で、最初にドイツで刊行されたのは2010年のことだった。ジャーナリストのアン・ヘレン・ピーターソンが「ミレニアル世代の燃え尽き症候群」を取り上げる10年近くも前に、ハンは「過剰な生産、過剰な業績、過剰なコミュニケーション」から生まれる「肯定性の暴力」と彼が呼ぶものを突き止めていた。わたしたちは、主にインターネットによって過剰な刺激を受けているために、逆説的にほとんど何も感じず、理解もできなくなっているという。
ハンの文章でひとつ皮肉なのは、彼が嘆いているまさにそのルートで簡単に広まることだ。ハンは自分の見解を飾り気のない簡潔な文章に凝縮するので、読者はあたかもその考えを自分で思いついたかのように錯覚する。いまや『疲労社会』をはじめとするハンの著書は、YouTubeの解説動画やTikTokの要約動画で数え切れないほど紹介されている。ハンの考えにとりわけ共鳴しているのが、芸術家やキュレーター、デザイナー、建築家といった、美とかかわる仕事をしている読者だ。それに対して哲学の研究者からは、ハンはあまり受け入れられていない(17年に『Los Angeles Review of Books』誌に掲載された評論では、ハンを「いまをときめく哲学者の候補として引けを取らない」と慎重に形容している)。
ハンの著書は10以上の言語に翻訳されている。スペインの『El País』紙によると、『疲労社会』は南米、韓国、スペイン、イタリアで合計10万部以上売れているという。北京のミュージアムの館長は、「中国の美術界は彼に取りつかれている」とわたしに教えてくれた。スペインの著名な作家で批評家のアルベルト・オルモスに話を聞いたときには、彼はハンを「哲学の名DJ」と形容した。バルトやボードリヤール、ベンヤミンらの引用を紡ぎ合わせてキャッチーな組み合わせを生み出すからだ。Kポップのスター、BTSのRMは、23年に『Dazed Korea』誌のインタビューで『The Agony of Eros』をオススメとして挙げて、こう話している。「ひどく気が滅入るかもしれません。この本には、ぼくたちがいま経験している愛は愛ではない、と書かれているからです」
インターネットで浴びる過剰な情報
わたしが最初にハンと出会ったのは、『Non-things』(未邦訳)だった。独立系書店の小出版社コーナーに目立つように置かれているのを見つけたのだ。わたしはその難解なタイトルと、表紙を飾るポストモダンなコラージュに引き寄せられた。都市の内側から見た摩天楼の写真と、真上から撮影した摩天楼の写真とがつなぎ合わされて、ビル群が抽象的な幾何学模様に見える。
ハンは『Non-things』のなかで、インターネットで浴びる過剰な情報、つまり「non-things」によって、世界に存在する物体を体験することから目をそらされていると主張している。「デジタルスクリーンは、わたしたちが世界をどう体験するかを決定し、わたしたちを現実から切り離す」。ハンの著作を読む最良の方法は、聖書を読む最良の方法と似ている。ざっと目を通していき、グッとくる1行を見つけたらそこから読み進めるのだ。一文一文がその本の縮図であり、一冊一冊が全作品の縮図になっているので、読者はそれほど深掘りしなくても論点を理解できる。
またハンは、「スマートフォンは携帯型の強制労働収容所であり、わたしたちはすすんで自分を抑留している」と書いている。じつに刺激的だ。じっくり考えたくなる禅問答であり、読んだとたんに画面を見つめている自分が嫌いになる。わたしは、読んでおかなければという気持ちに駆られて読み続けた。ハンが救いの道を示してくれるかもしれないからだ。
米国では4月初めに、ハンの最新の英訳本『The Crisis of Narration』が出版された(まるでマンガのように、複数のエピソードからなるひとつの長い物語が次々と刊行されている。Polityから出たハンの著書は表紙がすべて似通ったデザインで、統一感のあるビジュアルでブランド化されている)。同書で論じているのは「ストーリーテリング」の衰退だ。ストーリーテリングとは、インターネットで消費される箇条書きや編集済みの断片的コンテンツが支配する時代において、意味を築き上げる絶滅寸前の様式なのだ、とハンは主張する。
同書は『Non-things』の主張を土台にしているが、ハンは、現実に存在する物体の欠乏を嘆く代わりに、「現実の瞬間」を語りに変換するわたしたちの能力を嘆いている。「デジタルプラットフォームでは、語りよりデータのほうが価値が高い。『語りによる内省』は求められない」。だからInstagramに記録したわたしの日常は全体として見たときにまとまりがないのだろうか。あんなに時間と労力をつぎ込んで、自分のアカウントをキュレーションしているというのに。語りというものがデータに頼らないタイプの想像力を要するのに対して、ハンの考える「情報」はその対極に位置し、「コンテンツ」と共通する部分がある。
コンテンツという包括的な言葉は、21世紀の文化をよく表していると同時に、それを区別のつかない大量のごった煮に変えてしまう。『The Crisis of Narration』でハンは次のように語っている。「後期近代のデジタル社会では、ひっきりなしに投稿し、『いいね』し、シェアすることで裸の状態──人生の意味が欠如した状態──を覆い隠している。コミュニケーションやインフォメーションのノイズがあれば、日々の恐ろしいむなしさを確実に隠しておけると考えられている」
これを読むと、インターネットに毒された脳が勝手にこう反応する。「マジで最高だ!!! ビョンチョル・ハンにならトラックでひかれてもいい」。SNSの住人なら、ハンの著書を読んで、こき下ろされた気分と認められた気分の両方を味わうだろう。若い世代にとってのイケてる哲学のおじさまといった地位は、めったに拝めないハンの姿を読者が見たときにいっそう強まる。写真では、ハンはたいてい黒を基調とした服装で、着古してはいるが品のあるレザージャケットをはおり、細いマフラーを身につけていることが多い。長髪は後ろにまとめてポニーテールにし、肌はインフルエンサーのようにつやつやだ。
そのテレビ映えする容姿とは裏腹に、ハンはメディア業界から隔絶している。SNSのアカウントももっていない。『El País』紙による希少なインタビューでは、一日に書くのはせいぜい3行で、あとは植物の世話をしたり、ピアノでバッハやシューマンの曲を弾いたりして過ごすと話している。ハンから漂うオフラインのオーラ──自らをブランド化しているとわたしたち臆病なネット民は言いたくなるが──は、ほかの人にはない英知を備えている証拠に見える。
「突っ込みどころはたくさんある」
オックスフォード大学大学院(英語英文学専攻)の博士課程の学生で、インターネットに関する文献を研究しているチャールズ・ピジョンは、ハンの著作を次のように表現した。「少し古風なヒューマニズムという感じ。そこから何が得られるのかというと、自分と世界との関係や自分の生き方との関係を見直すような何かだ」
ただし、簡潔で遠大なハンの意見表明は、よくよく精査するとつじつまが合わない場合もあると、ピジョンは付け加えた。「突っ込みどころはたくさんある」。例えば『疲労社会』の主張だ。人類は障壁を特徴とする「免疫学的社会」から、境界も摩擦もない循環を特徴とする「ニューロン的社会」にシフトしたという箇所である。いうまでもなく、新型コロナウイルスのパンデミックを契機に、免疫学的に組織された世界へと極端な回帰が起きた。そうした社会が完全に消えたわけではなかったのだ。「あの切り詰めた明晰さみたいなものは、彼の文章が機能するうえでとても重要だが、ひどい間違いにつながるリスクのひとつでもある」とピジョンは語る。
とくに『The Crisis of Narration』では、話題とする対象からあまりにも苦々しげに距離を取るというリスクを冒している。「現在、ナラティブがひどくもてはやされている」とハンは的確に指摘する。それには企業のマーケティングや高まるTEDトーク人気に見られる「ストーリーテリング」熱も含まれるかもしれない。「ストーリー」が流行語になる一方で、語り(ナラティブ)によって意味をつくり出す、より深い本物の能力は失われたとハンは主張する(ここで彼が喚起するのは、「火のまわりに人が集まってストーリーを語り合う」という典型的イメージだ)。
ハンはSNSへの投稿を「ポルノ的な自己プレゼンテーション、あるいは自己宣伝」と表現している。それはもっともだろう。しかし、デジタル空間には意義深い経験をつくり出す可能性もあることが、ハンの著書ではほとんど認知されていない。21世紀のいまになってもこの点を見落としているのはユニークにすら思える。ハンの著書を読むのは包括的な正統派の思想を求めているからではないし、搾取と解放の両方の表現形態を育んでいるTikTokの逆説的あり方を理解していないからといって、60代の人間を責めるのは酷だろう。とはいえ、ハンには見落としている点がある。SNSによって、自らをナラティブに変えること、つまり自己のアイデンティティを構築し反映することが可能になった点だ。こうした自由は、伝統的メディアというトップダウン型ヒエラルキーではありえなかった。多くの人にとっては、インターネットが新たなキャンプファイアーなのだ。
non-thingsであふれかえったインターネットの情報経済のなかで自分の考察が花開いていることを、ハンはどう受け止めているのだろうか、と思わずにはいられない。インターネットに関するものを読むときは、なんとしても答えや解決策を得たいと考えがちだ。テクノロジーは善か悪か。どうすればそこから逃れられるのか。ハンには解決策や箇条書きのライフハックを提供するつもりはさらさらないが、その文章はインターネット上で、使い勝手がよくてわかりやすい教訓へと簡単に変換されかねない(TikTokにはこんなキャプションもある──「ビョンチョル・ハンと自己最適化 #資本主義 #マルクス主義 #セラピー」)。
ハンの著作は「過剰なデジタルの消費を批評しているが、それと相性もいい」とピジョンは指摘した。「検索エンジン向けに最適化され、人々が細切れに摂取できる、オシャレないまどきの思考セット」として利用できるのだと彼は続ける。「そこが真の落とし穴だ。話題にしようとしているシステムの外に身を置くことは不可能なんだ」。とはいえ、ハンの情熱的で武骨とも言える文体は、それ自体に語らせることを意図したものであり、その意味で、創作物の代わりに創作者が前面に立たされるデジタルカルチャーに抵抗してもいる。ペルソナを演じる必要はないというのも、ハンが読者に与えている啓示のひとつだ。
もしハンがTikTokに動画を投稿したら、それに対するコメントはおそらく、そのレザージャケットはどこのブランドのものかという質問で埋まるだろう(じつはわたしも知りたい)。それよりもわたしたちは、彼の著書をオフライン生活に踏み出すきっかけにすべきなのかもしれない。とはいえ、ハンの主張を実行に移すまでの間は、その本を自分が目指すシンボルとして持ち歩いたり、パラパラめくったり、友達に説明したりすればいい。アイダホ大学で学ぶマレーが言うように「ハンのクラスタは沸いている」のだ。
カイル・チャイカ|KYLE CHAYKA
『The New Yorker』のコントリビューティング・ライター。『The New Republic』『ニューヨーク・タイムズ・マガジン』などにも寄稿している。アイスランドの観光に関する記事が「The Best American Travel Writing 2020」に掲載。著書にミニマリズムの歴史をひも解いたノンフィクション『The Longing for Less』(2020年)。アルゴリズム技術が文化に与える影響を探る『Filterworld』。
(Originally published on The New Yorker, translated by Megumi Kinoshita/LIBER, edited by Michiaki Matsushima)
※『WIRED』による哲学の関連記事はこちら。
雑誌『WIRED』日本版 VOL.52
「FASHION FUTURE AH!」は好評発売中!
ファッションとはつまり、服のことである。布が何からつくられるのかを知ることであり、拾ったペットボトルを糸にできる現実と、古着を繊維にする困難さについて考えることでもある。次の世代がいかに育まれるべきか、彼ら/彼女らに投げかけるべき言葉を真剣に語り合うことであり、クラフツマンシップを受け継ぐこと、モードと楽観性について洞察すること、そしてとびきりのクリエイティビティのもち主の言葉に耳を傾けることである。あるいは当然、テクノロジーが拡張する可能性を想像することでもあり、自らミシンを踏むことでもある──。およそ10年ぶりとなる『WIRED』のファッション特集。詳細はこちら。